「記者の仕事」と聞いて、どんな姿を思い浮かべますか。
ニュースを取材している人、インタビューをしている人―。どれも正解ですが、実際の仕事は、もう少し奥深いものなのです。
楽待には、「記者職」という職種があります。記事を書くことはもちろん、そのために欠かせないのが「取材」。
けれど、取材とは単に話を聞くだけではありません。
テーマによって、聞く内容も、会う相手も、取材の進め方もまったく変わります。
今回は、不動産投資メディア「楽待新聞」の記者たちが、どんな工夫や思いを持って取材に臨んでいるのか。そのリアルな仕事の姿を、記者自身がご紹介します。
「人の話を聞いて、伝える」仕事
記者は、小説家でも評論家でもありません。自分の考えを語るのではなく、だれかの話を聞き、その方の経験や考え方をわかりやすく整理して伝える。それが記者の仕事です。
その「人の話を聞く」という行為こそが、「取材」です。
ただし、「人の話を聞く」だけでもないのが取材です。相手の言葉の背景にある思いや価値観、そうしたものを丁寧にくみ取る必要があるからです。
「一問一答」のように質問をただ並べていても、取材対象者から素直な感情や本心を引き出すことはできません。相手の表情、声のトーン、間の取り方など、細かな変化から「本音」を感じ取りつつ、会話をしながら、記事執筆のために必要な情報を聞いていきます。

テーマや目的に合わせて変わる「取材のかたち」
取材には決まったマニュアルはありません。記事の目的によって、質問の内容も取材相手も大きく変わります。
たとえば以前、「井戸のある物件を買うことの是非」をテーマにした記事を執筆しました(ちょっとマニアックですが…)。
「井戸物件はやめておけ」? トラブルに遭遇した投資家が明かすホンネ
この時は、井戸のある物件を購入・運営したことのある大家さん4人に、それぞれの考えや経験を聞きました。
1回の取材はそれぞれ40分ほど。短い時間ではありますが、それぞれの共通点や違いにも着目しつつ、どんな体験をしてきたのか、そこから得られた学びや知見は何かなど、角度を変えて質問を重ねます。
その結果、取材を通して「井戸物件に大家さん自身のメリットはない」という結論が導き出されたため、それを強調する形で記事執筆を行いました。
こうした工夫もあり、通常の2倍近い「いいね」の評価を獲得した記事になっています。
一方、1人の投資家の人生に焦点を当てた「インタビュー」取材もあります。取材時間は数時間ほど。時には1日密着することもあります。
その大家さんがどういう半生を歩み、どんなきっかけで不動産投資を始めたのか。成功や失敗、そこにある感情まで深く掘り下げていきます。
「子供の時はどんな性格だったんですか?」「一番うれしい瞬間って?」「二度としたくないと思うほどの後悔ってありますか?」「その時、なんで○○はしなかったんでしょうか…」「ちなみに、普段のお休みは何をしているんですか?」
幅広く、そして深掘りもしつつ、さまざまな観点で質問をすることで、いろんな回答をいただくことができ、記事としてまとめたときに「厚み」の出る内容になるのです。
たとえば、「廃墟収集家」を自称する投資家さんのインタビューを行った際には、実際に物件を見せていただきながら、お話を聞きました。
普段は高校で教師をしているというこの投資家さんには、投資のお話はもちろん、「AI時代に必要な能力」「大学入試について」なども語ってもらいました。記事には書ききれないほどの「講義」内容に、記者自身もとても勉強になったといいます。
「物件情報が絶えず舞い込んでくる」のはナゼ? 「廃墟収集家」の大家が4年で17戸の物件を買えたワケ
楽待新聞の記者「ならでは」の視点
一般的な新聞社などでは、社会的影響の大きいニュースや速報性のある出来事を追うことが多く、「誰にでもわかりやすく伝えること」が求められます。
一方、楽待新聞が届けるのは、不動産投資家という明確な読者です。
そのため、楽待新聞の記者が重視するのは「読者が実際に再現できるか」「本当に役に立つか」という視点です。
もちろん、我々も法改正や市場動向、速報性の高いニュースも扱います。それでも、「この情報が投資家にとってどう役立つのか?」「どこを掘り下げれば、役に立つ情報になるのか?」を常に考えながら取材しています。
単なるニュースを並べるのではなく、本質に迫り、「ここでしか読めない記事」を作ることを目指しています。
取材を成功させるための準備と工夫
面白い、ためになる記事にするためには、取材の前にどれだけ準備できるかも鍵になります。
取材相手のSNSをくまなくチェックし、過去のインタビュー記事や著書があればすべて目を通します。その人の考え方や表現のクセ、得意分野を把握することで、初対面でも自然な会話を心がけます。
もちろん、テーマによっては今まで知らなかったような法律や制度などについても、勉強してから取材に臨む必要があります。
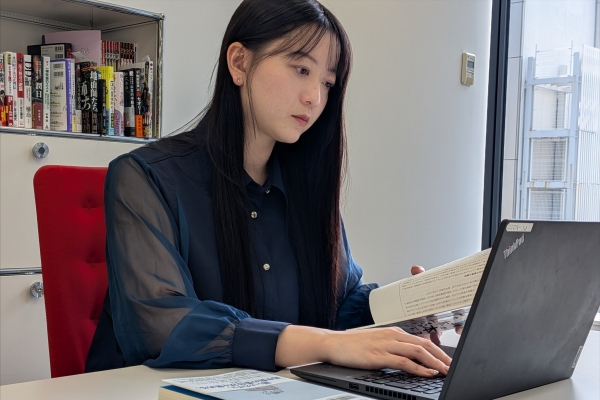
取材は「会話」と言えど、何の準備もなしに全ての要素を聞き出すこともできません。事前の「質問づくり」にも時間をかけています。「はい」「いいえ」で終わらないことも意識しながら、話が広がるように順番を組み立てていきます。
また、普通の会話ならためらってしまうような内容であっても、記事に必要であれば話してもらうのが難しいテーマについても聞かなくてはいけません。たとえば「一番の失敗談」や「損失額」などです。
こうしたことも含め、取材では「会話」として信頼関係を築くことを大切にします。相手にとって話しやすい空気をつくりながら、真摯に耳を傾ける。まさに「傾聴」の姿勢が欠かせません。
もちろん、どんなに勉強しても、わからないことは出てきます。そんなときは知ったかぶりをせず、素直に聞く勇気も必要です。
取材の醍醐味
率直に言えば、取材はとても楽しい業務です。
普段の生活では出会えないような人の話を、直接聞ける機会はそう多くありません。多様な経験や価値観に触れ、学ぶことができる。そんな恵まれた立場にいると実感します。
特に、楽待新聞が扱うのは「不動産投資」という非常にニッチな世界の話でもあります。
投資家というと、もしかしたら「お金にシビアな人」というイメージを持つかもしれません。しかし、実際にお会いすると、本当にさまざまな価値観や人生観を持った方ばかりです。
会社員として働きながら副業として始めた人、DIYで楽しみながら古い空き家を再生させている人、専業大家として、さまざまな場所で、たくさんの賃貸物件を提供している人…。
数値や戦略だけでなく、「なぜその判断をしたのか」「失敗から何を学んだのか」といった人間的な部分を描ける。投資というテーマを通して、人の人生や価値観に深く触れられる。それが、楽待新聞の記者にとっての一番の醍醐味です。
一方で、取材は簡単なものでもありません。読者の役に立つ、あるいは読者が知りたい内容を、読者に伝わる形にまとめられるか。それは、全て取材にかかっているからです。
それでも、取材を終えたあとに取材をした方から「自分の経験を振り返る良い機会になった」と言っていただけるのはすごくうれしいですし、次への活力になります。
また、読者の方から「わかりやすく問題提起してくれた」などのコメント、反応をいただけるのもやりがいにつながっています。
言葉を通して人と向き合い、その思いを形にして世の中へ届ける。それが記者という仕事の魅力だと思います。
AIの時代、単に「文章を書くこと」であればAIが担ってくれることもあるでしょう。実際、楽待新聞編集部でもさまざまな部分でAIを活用しています。
しかし、誰かの「生の声を聞く」「本音を引き出す」といった観点、ひいては記事の質を高めるといった観点では、「取材」はますます重要になってきます。
◇
「人の話を聞くのが好き」「言葉で伝えることに興味がある」。そんな方に、記者職はきっと向いています。
取材を通して、人の人生や価値観に触れ、それを読者に伝える。そんな仕事に少しでも惹かれた方は、ぜひ楽待の記者職に挑戦してみてください。